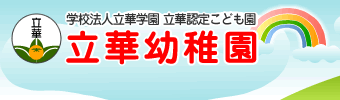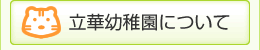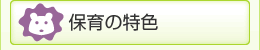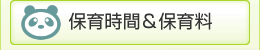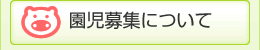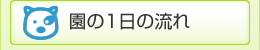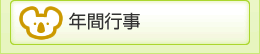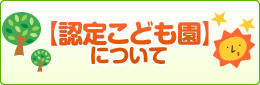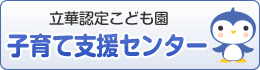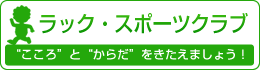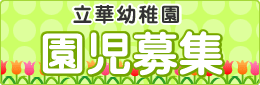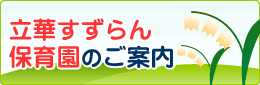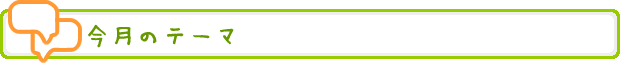立華だより 2017年2月
読解力
2月になりました。3日は節分・豆まき、そして翌日は立春です。まだまだ雪の日は続きますが、だんだんと春が近づいて来ます。
梅の花降り覆ふ雪を包み持ち
君に見せむと取れば清につつ
作者未詳(万葉集第十、一八三三)
春の訪れに雪が覆ります。そして気の早い鶯もやってきます。
梅が枝に鳴きて移ろふ鶯の
羽白妙に淡雪ぞ降る
作者未詳(万葉集第十、一八四〇)
梅の花の凛として いる姿が詩を詠ませてくれます。この時期ならではの光景が感じられます。
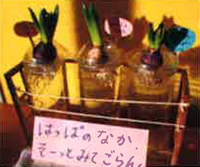 1月30日の読書新聞に「読解力が危ない」という記事がありました。昨年12月の国際学力調査では4位から8位になり、日本のこどもたちの読解力が低下しているというのです。
1月30日の読書新聞に「読解力が危ない」という記事がありました。昨年12月の国際学力調査では4位から8位になり、日本のこどもたちの読解力が低下しているというのです。
立華だより1月号でも取り上げたように国語力の養成が必要です。子どもがテストで応えられないのは問題文が理解できないために「何を聞かれているのかが分からない」が4人に1人程度いるというのです。
このことは、食事をするのに箸の持ち方が分からずに食事ができないようなものです。
まず箸の持ち方をしっかり身につけ食事が出来るように、文章を理解できる力を養成しなければなりません。そのために文章に親しむことはいうまでもありません。
幼児期に文章に親しむ経験がないと、小学校では文章が苦手になるでしょう。家庭でも幼稚園の立腰タイムでは文字に親しむために、漢詩や和歌を朗読しています。漢詩は朱熹の「偶成」です。
少年易老学難成
一寸光陰不可軽
未覚池塘春草夢
階前梧葉己秋声
少年老い易く 学成り難し
一寸の光陰 軽んずべからず
未だ覚めず 池塘春草の夢
階前 の梧葉 己に秋声
子どもたちはこの詩を二学期で朗読ができるようになりましたので、三学期は朗吟に取り組んでいます。
朗吟は歌で表現するので心のわだかまりを洗い流してくれます。そしてみんなと一緒に朗吟することによって仲間意識が育ち、そして立華っ子の読解力が身につくように願っています。